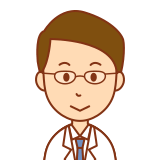
今回は「丸つけの極意!」というお話をしていきます。
問題を解いたら、「丸つけ」をしますよね。
その「丸つけ」1つにとっても効果的か否か、大きな分かれ目となってきます。
日々生徒さんの勉強を見ていて、「丸つけの方法を見直せばもっと良いのにな」と思うことが多々あります。
今回は効果的な丸つけについて、お話していきます。
丸つけの重要性について
効果的な丸つけについてお話しする前に、「丸つけの重要性」について説明いたします。
結論から申しますと、「間違えた問題こそ学びがある」ところにあります。
「問題を解いて間違ったしまった問題=自分に足りないところ」なんですね。
学校や塾の授業を受けて理解したつもりでいても、いざ問題を解いてみると間違ってしまうケースって多々ありますよね。
それはわかっていたつもりでいただけ、つまり「本当に理解できていなかった」ところになるんですね。
成績を上げるためには、自分の足りないところを「問題練習→丸つけ」で確認していく作業が必要になってきます。
よく丸つけが面倒で、問題を解きっぱなしで終わっている生徒さんがいます。
それだと自分がきちんと理解できているか分からないまま進んでいることになります。
せっかく時間を使って問題を解いたのに、非常にもったいないことだと思いませんか?
問題を解いたらしっかり丸つけをして、必ず理解度を確認するようにしましょう!
次の章から丸つけのポイントについて解説していきます。
丸つけの極意①「細かく丸つけする!」
丸つけの極意①は「細かく丸つけをすること」です。
何ページも問題を進めて、まとめて丸つけをする生徒さんを多く見ます。
それだと一番最初に解いた問題の記憶が薄れてしまっています。
「あれっ、こんな問題解いたっけな!?」という状態で丸をつけても、学習効果は薄いです。
こまめに丸をつけていって、問題を解いた記憶があるうちに確認するようにしましょう。
オススメは、「1ページ問題を解いたら必ず丸つけをすること」です。
コンスタントに丸をつけていって、その都度、自分の理解度を確認するようにしていきましょう!
丸つけの極意②「しっかり解説を読む!」
丸つけの極意②は「しっかり解説を読むこと」です。
特に間違えた問題は、しっかり解説を読んで理解するように努めましょう。
正直、当たり前ですよね。
ですが私の経験上、その当たり前ができていない生徒さんがかなり多いです。
以前、ものすごいスピードで大量に問題練習をしている生徒さんがおりました。
ですが成績が一向に上がってこないので、どのような勉強をしているのか細かく聞いてみました。
すると間違えた問題の解説を全く読んでいなかったというのです。
ただただ問題を大量に解いても、なかなか効果は表れません。
自分の理解が足りていないところを解決できていないのですから、当然です。
間違えた問題の解説はしっかり読むこと、それでも分からない問題は質問して「とにかく解決することを大切に!」と指導したところ、成績は急上昇しました。
また間違えた問題だけでなく、「何となく正解していた問題」に関してもしっかり解説を読んでおきましょう。
理解があやふやなままでいると、次の類題で間違ってしまいます。
「解決すること」、これを強く意識していきましょう。
丸つけの極意③「自分の答えは消さない!」
丸つけの極意③は「自分の答えは消さないこと」です。
間違えると、自分の書いた答えを消しゴムで消してしまう生徒さんは非常の多いです。
それだと「自分がどこでどう間違ったのか分析できない」からです。
分析というと難しく感じてしまうかもしれませんが、あとで自分が間違えてしまったところを見返すだけでも十分効果があります。
自分の答えを書く、間違えてしまった問題は解答を書く、これだけでも書くことは多いですから、ノートはたっぷり余白をとって、贅沢に使用することも大切です。
私の生徒で以下のようなノートの使い方をしている生徒さんがいます。
1ページを半分にし、自分の答えと間違った問題を分けて書いています。
自分がどこでどう間違ってしまったのか、よく確認できるノートだと思います。
参考にしてみてください!
最後に
今回のお話はいかがだったでしょうか。
丸つけ1つとってみても、大事なポイントがいくつもあることがご理解できたかと思います。
せっかく貴重な時間をとって勉強するわけですので、学習効果が上がる方法を実践してほしいと願っております。
このようにスタゼミでは、勉強・受験・進路に関する情報を発信しております。
勉強や進路のことで何がお悩みやお困りごとなどございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
個別に相談させていただきます。
それでは次回の記事もよろしくお願いいたします。




