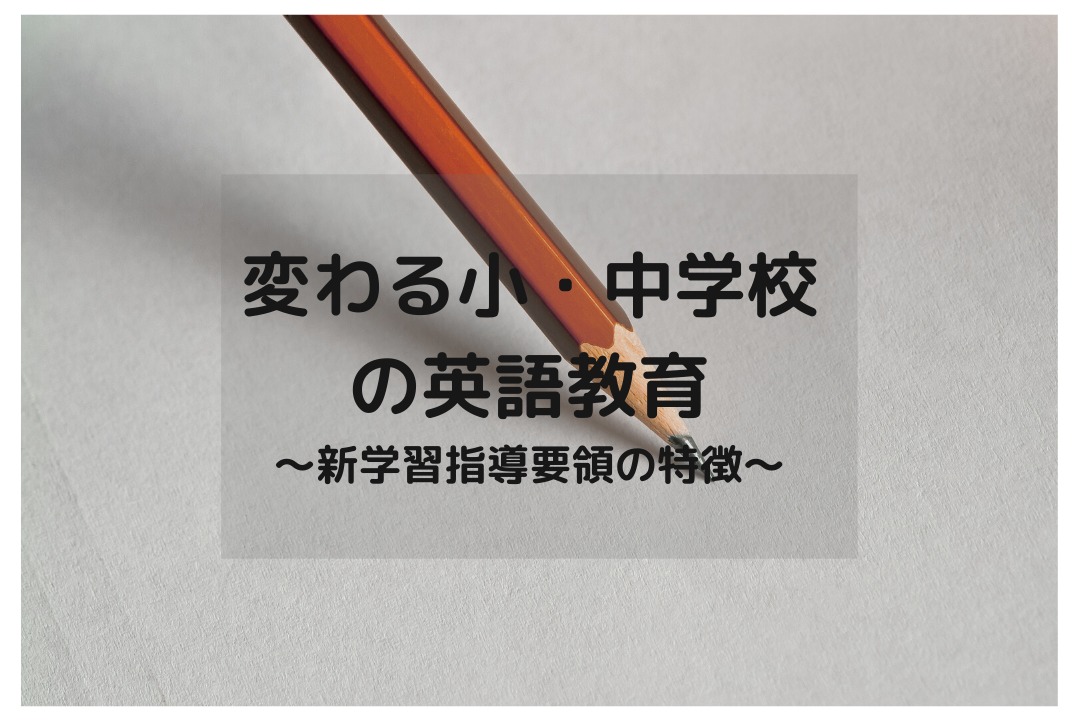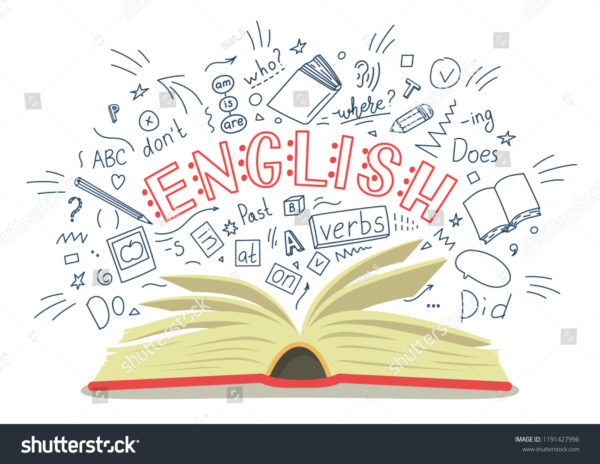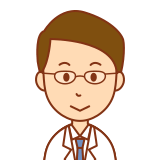
今回は今後の小学校・中学校の英語教育についてのお話です。2020年度の学習指導要領の改訂により、英語教育の中身が激変しています。
小学校の英語導入について
新学習指導要領の移行措置期間として、2018年度から小3~小6まで、英語の授業が始まっています。
2020年度からは小学校で新学習指導要領が全面実施され、小3・4は「外国語活動」、小5・6は「外国語」という教科として導入されています。
「外国語活動」とは、ALT(外国語指導助手)と一緒に行う活動であり、「聞く」・「話す」が重視されます。どちらかというと英語に親しむというニュアンスが強いです。一方、「外国語」は学級担任と専科指導を行う先生(英語を専門とする先生)が指導し、「聞く」・「話す」加え、「読む」・「書く」が重視されます。いわば中学校で行う授業に類似した形といえるでしょう。
小学校で英語が本格的に教科化されたため、自動的に中学校の英語も難化することになります。例えば、小学校の英語で習う英単語は600~700語になり、中学校では現行の1200語程度から1600~1800語習うことになります(中学校での教科書改訂は2021年度より)。
具体的な改訂ポイントは次の項目にまとめます。
新学習指導要領「英語」の改訂ポイント
| 1.小学校では小3・4年生は「聞く」・「話す」を重視した「外国語活動」、小5・6年生は「読む」・「書く」も加えた「外国語」として設定される。
2.学習する英単語は、小学校で600~700語程度、中学では現行の1200語程度から、1600~1800語程度へと変更。 3.小学校英語の導入により、中学校の英語文法に「原型不定詞」・「現在完了進行形」・「仮定法」が追加。 |
いかがですか?修得すべき英単語数の増加に加え、中学校で習う新たな文法内容に衝撃を受けました。
英単語数は今まで中学校において1200語程度だったものが、小・中学校合わせて2200~2500語程度、およそ2倍の数に跳ね上がります。
「原型不定詞」・「現在完了進行形」・「仮定法」は今まで高校で習う文法です。この内容を中学で追加するのは、生徒にとってはかなりの負担を強いられることになると思われます。
新学習指導要領「英語」についての考察
私の考察は以下の通りです。
①日本語の修得の方が最優先ではないか。
これは一般的な意見でも上げられているところです。
日本語の修得もままならないのに、新たに英語を加えても大丈夫なのかという不安はあるかと思います。
確かにその通りなのですが、考え方を少し変えると、英語の学習から日本語の気づきや学びも期待できるところが言語学習にはあります。ですので、一概に日本語優先ばかりを主張できないのでは?と感じています。
しかしながら国語が弱い子どもたちが増えてきているのも、塾の仕事を通じて感じているので、まずは日本語をしっかり勉強するという主張も否定できません。
日本語優先は賛成か、反対かは難しい論点ですが、私は小4までは日本語のみに注力すべきであると考えています。
「小4の壁」という言葉があるのですが、小4になると学習面でのつまずきが目立ち始める子どもが多くなり、その原因はこれまでの学習の積み重ねの不十分さであると言われています。
ですので小4までは国語の学習をしっかり行い、小5・6年生から英語を始めるという流れが、最もよいと考えています。
②“英語嫌いな生徒”の増加
いわゆる“英語嫌いな生徒”がますます増えていくのは避けられないでしょう。
現行の中学校の英語ですら、修得するのが難しい生徒が多いのが現状です。
今回の改訂により、小学校から英語に親しむ活動を通して、英語への距離を縮められるかもしれません。
ですが英単語数の増加は相当なものですし、高校から降りてくる文法内容もかなり高度なものとなります。
いったん英語に苦手意識が芽生えてしまうと、払拭することは大変困難になります。そのきっかけを与えてしまうような学習指導要領になっていると言わざるを得ません。
③得意な生徒はますます伸びる
②の逆で、英語が得意な生徒にとっては、ぐんぐんと実力が伸びていく内容になっていると思います。
小学校から塾などの民間教育で、すでに英語を始めていたり、英検などの資格試験を経験していたりする生徒さんが多いのが現状です。
早い学年のうちから英語が好きで得意であれば、英単語量を増やし、文法内容をどんどん先取りして学習していくことで、英語の成績はぐんぐん上がっていきます。
これまでの難関私立高校の入試でも、原型不定詞や仮定法は出題されてきた内容ですので、勉強できないことはないです。
ですがそういった生徒はごく一部です。多くの生徒は現行の英語の学習範囲でも相当な勉強量をこなして、やっと中学内容を修得するというのが一般的です。
まとめ
以上、新学習指導要領の内容と考察をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。
新学習指導要領の導入で学習量が増えることにより、子どもたちの学力にますます差が広がることになると考えられます。
差ができるどころか、いわゆる“落ちこぼれ”な生徒が急増するのではないかという懸念も感じています。
大切なことは、差が広がらないように、苦手意識を持つ生徒が増えないように、どう指導していけばよいかを考えていくことではないでしょうか。
まさに教師の力量が問われてくる学習指導要領だと思います。
おそらく学校で指導しきれない部分も出てくると思われますので、民間教育の必要性もますます上がってくるでしょう。
公教育と民間教育との連携が本格的に求められる、そんな日が近いのは間違いないでしょう。