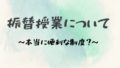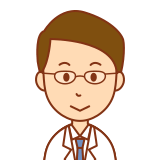
今回はたびたびニュースにも取り上げられている、小学校の教科担任制についてお話しさせていただきます。結論から申しますと、生徒にとってはもちろん、先生にも有益な制度であると思っております。
教科担任制とは?
まず教科担任制についてお話しします。
従来小学校では、学級担任制といって、クラスの担任の先生がほぼ全ての教科を指導してきました。
中学校になると教科ごとに先生が異なります。
これが教科担任制です。
英語であれば英語専門の先生、数学であれば数学専門の先生が授業を行います。
小学校においても専門の先生が指導した方がいいのではないか?という議論が起こりました。
その結果、2022年度をめどに小学校高学年において教科担任制を導入する方針で動いているという状況です。
教科担任制は賛成?反対か?
先ほども申し上げましたが、この制度の導入について、私は基本的に賛成です。
一例として塾生から聞いた話をさせてください。
小学校の英語教育ですが、私の塾生にどのような授業をしているのか、ヒアリングしたことがあります。
その塾生が言うには、担任は英語については全くの無知であり、ほとんどの内容をALTの先生に任せっきりだったそうです。
ALTの先生がいないときは、英語が得意な生徒に発音させ、担任の先生はほとんど英語を読まなかったそうです。
確かに問題のある授業だったかもしれませんが、その先生を一概には責められないと思います。
小学校の先生も自分の専門科目というものがあり、得手不得手があるかと思います。
全ての教科を教えるのは難しいことですし、特に高学年になればなおさらです。
小学校高学年の内容は、大人が想像するよりも難しく深い内容になってきますので、教科担任制は非常に有効な手立てであると考えられます。
教科担任制が実現され指導教科を絞れれば、より教科の専門性が増し、授業の質の向上にもつながります。
学校の先生にとっても指導教科が絞れた方が、準備もしやすいでしょうし、授業へのモチベーションも上がるのではないでしょうか。
※ココで1つ余談を
これは塾業界でよく言われる話なのですが、5教科(中学校)全て教えられるという先生は、あまり信憑性を感じないというものがあります。
5教科教えられると聞こえは良いですが、全ての教科について中途半端な知識しかないと受け取られる傾向があります。
実際そのような先生の授業は、「わかりにくい」という生徒の声を聞いたことがあります。
指導可能科目が1、2科目くらいの先生の方が、より専門的で教え方もより熟知されている傾向があるといえます。
教科担任制のメリット・デメリット
メリット
・より専門的でわかりやすい授業が期待できる
これは上記で述べたとおりですね。
・多くの先生たちで生徒を見ることができる
これも教科担任制の大きなメリットです。
従来の学級担任制ですと、ほぼ担任1人が生徒を見ます。
生徒の様子をじっくり見ることができますが、多くの先生たちから見てもらうことにより、担任には気づかないところを指摘してもらえる可能性が高くなります。
つまり複数教師で多面的な児童理解が実現できるということです。
1人の目では気づかれない部分を、他の先生から気づいてもらえることで、救われる子どももいるかもしれません。
何でもそうですが、多角的な視点は多くも利点をもたらすことにつながります。
デメリット
・教師間の連携が最重要であること
もし教師間の連携がなされないと大きなデメリットになるということです。
とにかく教育現場は忙しいです。
授業以外にも様々な仕事を教師は抱えています。
そうすると教師間のコミュニケーションが不足し、教科担任制のメリット、多面的な児童理解がなされなくなってしまいます。
ともすると1人ひとりの児童を深く理解している教師がいなくなる可能性も出てきてしまいます。
教科担任制を導入するのであれば、教師間のコミュニケーションは最重要項目です。
一日の中で必ず話し合いの機会を持つようにし、子どもについて気づいたことを共有する時間を持つようにしなければなりません。
最後に
いかがだったでしょうか。
教科担任制はとても有効な手段です。
特に学習面においてはこの上ない手立てだと思います。
ですが取り扱いを誤ると、子どもたちの心のケアという部分で大きな欠落が生じてしまいます。
新しい制度を導入すると、先生たちもすぐには慣れないものです。
「教師間のコミュニケーションの時間」、これを1日の仕事の最重要項目として位置づけて欲しいと思います。